ふさわしいテンポとは?
チェンバロスタジオからの帰宅途中に買い物に立ち寄ったスーパーで、ピアノのBGMが流れていました。何だか普通のBGMっぽくないと思ってよく聴いたら、ん? これ、ヘンデルだ! しかもマイナーな小品。ヘンデルが生前に出版せず、自筆譜で伝承されている習作だったはず。こんな曲がこんな所で聴けるなんて嬉しい! でも・・・。
一度はコンサートでも弾いて、今でも大体暗譜している曲ですから、聞き流すわけには行きません。とにかく気になるのがテンポです。速すぎます。私なら、というか、チェンバロ奏者ならこんなに速くは弾きません。
それでも、自分ならどう弾くかということを脇に置いて客観的に聴いてみると、ピアノなら案外みんなこのテンポで弾くかもしれないなという気がしてきました。このごろ私はピアノでのバロック音楽の演奏は全く聴きませんが、そういえばバッハのインヴェンションでもフランス組曲でも、ピアノの録音ではアレグロがやたらに速かったのを思い出しました。
どうしてピアノだと速く弾くんだと思いますか?
答は一つではないと思いますが、端的に言えば「時間当たりの情報量」の違いです。分かりやすく説明しますね。
まず注目したいのが音色の違いです。ピアノの音は丸いです。チェンバロの音には倍音がたくさん含まれます。ピアノでゆっくり「ドレミファソ」と弾いただけではつまらなくても、チェンバロで弾けばそれだけで充実したひとときに感じられます。倍音が豊かなので、チェンバロで弾く一つの音には、ピアノならオクターブを重ねるのと同じくらいの存在感があるからです。ロマン派以降のピアノ曲で、右手にも左手にもオクターブや和音がたくさん出てくるのはそのためです。
スーパーで流れていたヘンデルの曲は2声から3声です。右手も左手も1つか2つずつの音しか同時に弾きません。チェンバロならそれで十分に充実して聞こえるのですが、ピアノだと物足りません。右手も左手もオクターブにしたり和音にしたり編曲すればピアノでも充実するのでしょうけれど。実際、ピアノを想定したヘンデルの古い楽譜で、「2声の曲には内声をたくさん補うべき」と前書きで論じた上で4声5声に編曲してしまった原典版(とは言えないですよね)を私も持っています。
とは言っても、作曲家が書かなかった声部を、ピアノだと物足りないからという理由で勝手に追加して録音するのは勇気が要りますよね。そこで大抵のピアニストはテンポを上げます。そうすれば時間当たりの情報量が増えて、ぱっと聴いた感じでは充実した演奏に聞こえます。
ピアニストがバロック音楽のアレグロを速く弾くことの背景にはもう一つ、ロマン派以降のピアノ曲の特殊な語法に慣れ親しんでいることも挙げられると思います。ショパンでもドビュッシーでもいいですが、同じ時代の他の楽器や歌の楽譜と比べて、やたらに細かい音符が多いと思いませんか? 分析してみれば分かりますが、細かい音のほとんどは主要な音の間を埋める分散和音です。ピアノという楽器の音響特性にはこの特殊な語法が適しているのです。
ところが、バロック音楽のアレグロの細かい音は、それ自体が主要な音であることが少なくありません。一つ一つの16分音符に微妙なニュアンスを使い分けて丁寧に語る感じで、それにはある程度の遅さが必要です。ロマン派以降のピアノ曲での細かい音のように弾き飛ばしてしまっては、細かな意味が何も伝わらないという結果になりかねません。意味が伝わらなくては一層つまらなく感じるから、もっとテンポを上げて「時間あたりの情報量」を稼ごうということになります。
と、ピアニストがバロック音楽のアレグロを速く弾く理由として「時間当たりの情報量」を軸に考えてきましたが、もしかして、もっとずっと安易かつ根深い問題だったりして、という気もしてきました。それはこうです。
「他のピアニストの録音がみんな速いから。」
ヘンデルの曲を弾こうというときに、ヘンデルと対話する代わりに、現代の同業者はどう弾いているかを気にするのです。
私ですか? 私はピアノ演奏どころか、他のチェンバロ奏者がどう録音しているかも気にしません。聴いて「素晴らしい!」と感動したことは見習いたいですが、あの演奏とこの演奏を足して2で割ったら、とか、これらの何十もの演奏の平均値を求めると、とか、そういうことには興味がありません。
もちろん、「私のこの解釈は、とんでもない誤解だったりして・・・」と心配になることだってあります。でも、そういう解釈に行き着いた私の未熟さをそのままにして、見掛けだけ他の演奏家の録音から借りてきたって、私が演奏する意味がありません。ありったけの思いを作品に注ぎ込むには、たとえ間違っていても自分の本心から出た解釈であることが必須です。
過去の偉大な作曲家と直接向き合って、その精神を現代に伝える演奏家でありたいものです。
あなたのコメントをお待ちいたします
下のほうのコメント欄で、あなたのお考えをお聞かせくださると嬉しいです。
(システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

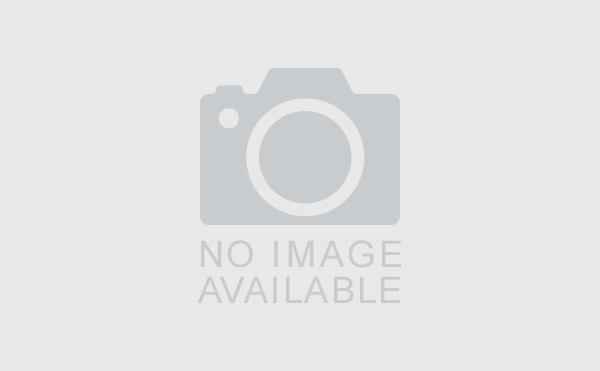
八百板先生を通じてバッハ大先生やヘンデル大先生とお話が出来たりするのをとても嬉しく思います。今日のお話も印象深く心に残ると思います。実は昔はチェンバロの音がとても聴きづらい気がしていたのですが、この頃はピアノの方がつまらなく思える事が…。倍音の有る無いに耳が慣れてきたのでしょうか。これからも楽しみにしております。
山下さん、嬉しいコメントをありがとうございます。
コメントを頂いて思い出しましたが、私も昔は「あの楽器の音は好きじゃない」とか「この楽器で弾いてさえいれば演奏がどうでも気にならない」とか、表面的な好き嫌いで音楽を聴いていたと思います。山下さんも、音楽の聴き方がどんどん深くなっていっていくと、同じものを聴いてもたくさんの幸せが得られるようになりますね。
聴き方が深くなるという点ではバッハの音楽の深さを味わう事が出来るようになってから不思議と現代音楽にも耳を傾けられるようになってきたという点です。以前はラジオ番組で流れてくる演奏会の音楽でも聴くことが出来なかったのがここ1~2年で聴いていても苦ではない気がしています。
バッハで体験した和声の複雑さに驚き、また演奏する事で自分の中にその免疫が出来たのでしょうか?(笑)。とにかく私にとってバッハの世界はまだまだ未知なる宇宙のような世界です。
バッハの和声の複雑さに「免疫」ですか? おもしろい表現ですね!
たしかに、バッハの和声は複雑です。晩年のバッハになると、古典派もロマン派も飛び越えて、20世紀音楽のようです。「先に和声進行を設定して、それに合うように各声部を作る」という当時の一般的な作曲の仕方を超えてしまったんですね。各声部の旋律が、ある意味で和声などお構いなしに動きます。そのことで、ものすごく高度な対位法が可能になったのだと思います。
バッハやバロックに限らず現代のクラシック音楽、特にピアノ作品は、馬鹿げた速弾き競争に陥っている。
単なるテクニックの見せびらかしに過ぎないと思います。
根深い問題ですよね。
良心的なピアニストが作曲家との対話から導き出された落ち着いたテンポで演奏しようと思っても、聴衆の基準がその「馬鹿げた速さ」になってしまっていれば受け入れてもらえないでしょうから。結局は聴衆が賢くならなければ解決しないのでしょうか。
バロック時代は通奏低音をいろいろアレンジして状況にあわせたけど、古典以降は作曲家が仕切る、だから通奏低音(伴奏)の自由度が否定されカデンツァなんかも結局は指定され、そうするとピアニストが技量を発揮できるのは超絶技巧(速度含む)になってしまい、また創造でなく譜を正確に追う(でもこれは電子のほうがうまい)ことが求められ、これがピアノの評価基準と限界との一因ではないかなと思っています(あと古楽器とちがって、プロが大型のを使う傾向も関係してそう)。もっと伴奏を豊かに楽しくできるといいのにと思うのですが。
ありがとうございます。
聴き手が「そんな演奏は要らない。もっとこういう演奏を聴きたい。」と発言することが、世界を変える力になると思います。20世紀の古楽復興もそうした聴衆の後押しのおかげでした。今、せっかくのその成果がなかなか広まらないのが歯がゆいですね。
八百坂先生のバッハ(小さな6つのプレリュード2番)を初めて聴いたとき、また、先生のなさる演奏を見たとき、大きな衝撃を受けました。
この曲は留学中、与えられた最初の課題曲でした。バッハの細やかな音の連なりはショパンなどのロマン派よりも難しいとも思われるのに、他の友人はもっと壮大に聞こえるベートーヴェンソナタなどを弾いていて、それらは一見人を圧倒しますが、バッハはただ地味で暗譜しにくい…
しかし、先生のチェンバロ演奏でこんなに「美しいバッハ」があったのかと感動いたしました。ロマン派のやたら細かくて難しい曲は、年老いてからは指もついていかなくなり、約40年前に留学中弾いていたモーツァルトやバッハやヘンデルにばかり、惹かれます。
トロントにいた頃のグレン・グールドのバッハに出会った理由もありますが、やはり
バロックは心に癒やしと落ち着きをもたらします。
嬉しいコメントをありがとうございます。
「バッハは本当は美しい」
この事を一人でも多くの方にお伝えするのが私の使命です。
通りすがりの者ですが、仕事でモダンオーボエを吹いています。今更ですが、テンポと一音一音の情報量の関係に気づき始めたところです。お考えにとても共感できました。最近オリジナルが弦楽用の曲のヴァイオリンパートをそのままオーボエ演奏する機会がありました。参考にしようと原曲の録音をいくつか聴きましたが、皆同じようなテンポのものが多かったです。それらの演奏は素晴らしかったですが、オーボエで演奏する場合はオリジナルの楽器で一般的に演奏されているテンポよりも速く演奏しないとなんだか都合が悪いなと思ったのですが、その理由はやはり一音一音の情報量の違いなんだと気づきました。私のオーボエの音よりもヴァイオリンのほうが、華やかな倍音も多いですし、微妙な音の細かい表情も表現しやすい分テンポがゆったりしていても成り立つのだと思いました。
私の場合は逆の立場になった訳ですが、作曲家が想定していなかった楽器でその曲を演奏する場合は特に気をつけようと思いました。
私自身昔バッハをピアノと二重奏、チェンバロと二重奏。どちらも演奏した事があるのですが、その時はよく考えもせずなんとなくしっくりくるテンポで演奏していたのですが、この記事を拝見させていただいて理屈が少しわかったような気がしてありがたいです。
話は少し変わってしまいますが、バッハ等はよくピアノで演奏されるのを聴きますが、クープラン等のフレンチバロックはピアノで演奏されているのを聞いた事がありません。たしかになんとなく上手くいかなそうな気はしますが、やはりあの独特な間というかなんというか…そんなものが難しいのでしょうか。チェンバロの真似は無理だと思うので、また違ったアプローチでうまくいけば…でしょうか?でもそれって作曲家が想定していた事では無いですよね…..考えすぎて頭がおかしくなりそうです笑
管楽器は時代によってだいぶ構造が変わっていて、それとともに音や、響きも変わっている中、バロックから現代の曲までを形にしなければいけないので、今回のお話とても参考にさせていただきました。
現代の楽器というのはまるで平均律のように器用貧乏感が否めないのですが、そんな中でも少しでも良い演奏ができるように精進したいです。
ありがとうございました。
長文失礼致しました。
大変に的確なコメントをいただきましてありがとうございます。お役に立てまして光栄です。
クープランがピアノでほとんど演奏されない理由を、私はこう考えています。
バッハのチェンバロ曲でも、特にインヴェンションや平均律クラヴィーア曲集などの対位法作品の場合、チェンバロを指定してはいても発想の元が合唱だったりオルガンだったりします。実際これらの曲の多くはオルガンで弾いてもじゅうぶん美しいです。なので、ピアノで楽譜どおりに弾くだけでも、そこそこ演奏がまとまりやすく作られていると言えます。
それに対してクープランは、チェンバロのことしか念頭に置かずに作りました。結果として、チェンバロで弾くならその楽譜で美しいけれど、他の楽器では全く形にならない、という特殊な音楽となりました。ある所で突然声部が増えたり、解決すべき音がしょっちゅう省略されたりしますが、それがチェンバロの場合だけ特別に効果的なのです。
高校生のときにインベンションを習っていて、発表会で1番を演奏しました。
緊張していたせいか、練習よりもかなりゆっくり弾いてしまい、先生からずいぶん丁寧に弾いていたわねといわれたことを覚えています。
案外正解だったのかもしれませんね。
これだけ録音や自動演奏が発達した現代ですから、演奏することの意味は「どれだけ心を込められるか」だと思います。
テンポが速い空っぽの演奏より、テンポが遅くても中身の濃い演奏のほうがずっと価値があります。
ご返信ありがとうございます。
つい最近まで、バッハというかバロックは機械的、無感情に弾くものと思い込んでいました。
とはいえ、平均律Ⅰの1番プレリュードは、ノンペダルより、ペダルを使ってゆっくり弾くのが気に入っています。きっとその方が音が重なって美しい和音が響くからですね。この曲だけはペダルを使っても良いという指示がある楽譜もありますが、バッハでペダルを使うのはどうなのという思いもありました。今回やっと、八百板先生の記事を拝見して、自分なりに得心しました。
高校卒業でピアノのレッスンをやめて以降、たまにいたずら弾きするくらいでしたので、定年退職後に一念発起してピアノを再開した当初は全く指が動かず(特に左手)ハノンや平均律のプレリュードもギッコンバッタンとしか弾けない状況でした。
最近やっと指がなめらかに動くようになってきており、平均律を弾くことを目標にして練習をしています。
とはいえ現在のレベルはインベンション第1番のおさらいがやっと終わったというところの初心者です。
たまたまYouTubeで出会った八百板先生の講座受講を始めたばかりですが、これからもよろしくお願いいたします。
平均律クラヴィーア曲集第1巻の1番の前奏曲は、チェンバロでも指で音を目一杯残して弾きます。こういう弾き方を通称「指ペダル」といいます。ピアノでペダルを使うのと同じように豊かに響きます。
平均律クラヴィーア曲集を目指していらっしゃるとはすばらしいです。ぜひ弾けるようになってください。
バッハの無伴奏のバイオリン曲は、教会などの残響時間の長い空間で演奏されることを計算して作られていると本で読んだことがあるのですが、やはりチェンバロの曲もチェンバロから出る倍音を計算して作られているのでしょうか。
私はそう思います。
といいますか、作曲家というものは目の前にある楽器が最高の効果を発揮するような音符を書くものです。これは計算してできるようなものではなくて、その楽器を巧みに操れる名手だからこそ自然にやってのけることだと思います。
返信ありがとうございます。
私はバッハのことに限らず、知らないことだらけですので、八百板先生の発信される情報から少しづつでも学んでいきたいと思います。
お役に立てれば嬉しいです!