バッハ先生ごめんなさい!
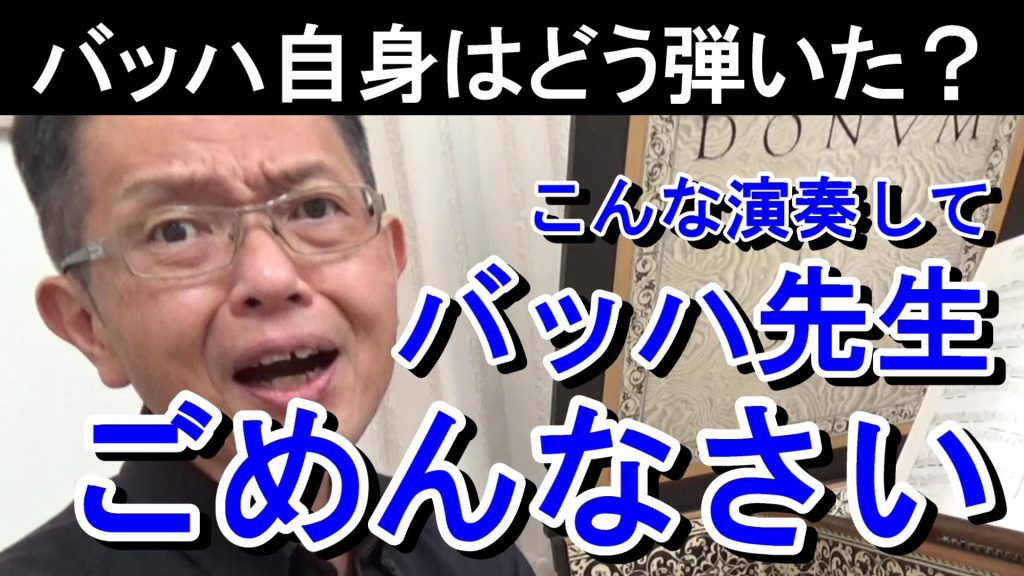
前奏曲をそんなふうに弾いたら「ぶち壊し」ですよ
曲はとっても短い「前奏曲 ハ長調」バッハ作品番号で939っていうんですけど、番号を聞いたって分からないですよね。
ピアノ教室でインヴェンションを始めるよりずっと前に生徒に弾かせることもあるみたいです。あなたももしかしたら弾いたかもしれませんね。
こういう曲は本当は楽譜どおりに弾くものじゃないんですけど、日本中のピアノ教室ではどんなふうに教えられているんでしょうか。
試しに始めの部分を楽譜どおりに、メトロノームどおりに弾いてみました。「ぶち壊し」ですよ。
詳しい議論は下の動画で。
(注:スマホなどで動画が表示されない場合、スマホ画面の右上メニューボタン(縦に点が3つ並んだボタン)を押して再表示(丸い矢印ボタン)すると表示されることが多いです。)
あなたのコメントをお待ちいたします
下のほうのコメント欄で、あなたのお考えをお聞かせくださると嬉しいです。
(システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

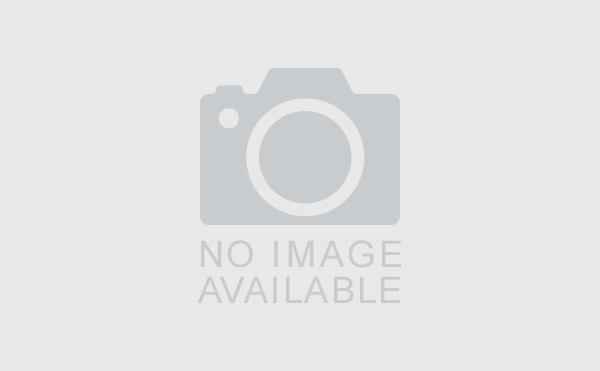
こんにちは。
新潟市りゅーとぴあが毎年夏に行なっている「オルガン・サマーデイズ」という企画があり、その中のひとつに、オルガン演奏経験の無い人でも参加OKの演奏体験会があります。私は幸い今年参加することができ、その時に今回御紹介の前奏曲ハ長調を弾きました。
この曲は、数年前からポツポツと練習していたのですが、堂々とした雰囲気もあり、チェンバロ曲のイメージの範囲に収まらない、オルガン曲(冒頭和音など、低音のペダルを使って長く伸ばす弾き方が合いそうです。実際、りゅーとぴあのオルガンで弾かせて頂いた時にもペダルを使わせて頂きました)や、管弦楽組曲やブランデンブルク協奏曲程度の規模の合奏曲(「序曲」のような壮麗な雰囲気で、オーボエやトランペット等管楽器も入れた華やかな編成のような)のイメージがしていました。
今回、八百板先生の仰る「即興曲」としての側面、なるほどと思いました。私の技術では、先生のような即興的な装飾を入れるまでには至りませんが、最後のスケール的な部分を機械的に弾かないように(私も練習時には、先生のように自然な緩急をつけられるよう目指して弾いていました)、自然界の山をえがく線のように、との御言葉、納得です。
この曲を、あの大オルガンで弾いたんですね!
それに「チェンバロ曲のイメージの範囲に収まらない規模の合奏曲」のイメージも持って下さったとは、嬉しいです。