チェンバロの弦の張り替え


世界的名器である、マルティン・スコブロネック製作のドイツ様式2段チェンバロです。何年ぶりかでこの楽器の弦を張り替えました。
チェンバロの弦を張り替えるのは、殆どの場合は弦が切れたときです。でも今回は違いました。ある弦の先端をピンに引っ掛けるための結び目が調律中にどんどん緩んで、どんなにチューニングピンを回しても弦が緩み続けるようになってしまったのです。この週末にこの楽器を含むスタジオ所蔵の4台の鍵盤楽器を全部使ったコンサートを控えています。いつまでも別のチェンバロで練習していては調子を取り戻せないので、今のうちに張り替えることにしたのです。
この弦は自分で張り替えた記憶がありません。真鍮弦ですが、その近くのほかの弦と同様に黒っぽく錆びています。少なくとも15年以上前に張られたものでしょう。
チューニングピンを緩めて引き抜き、古い弦を外して、新しい弦を張ります(1枚目の写真)。一台のチェンバロに使われる弦は太いものから細いものまで10種類以上を使い分けています。弦の太さを測るのには本当はノギスでは精度が足りなくてマイクロメーターがあるといいのですが、まあ太さの絶対値が精度良く測れなくても、比べる対象が手元に現物として揃っているのですから大丈夫です。
あるチェンバロ製作家からは「太さは測るより指でつまんでみれば同じ太さの感触のものを見分けるのは簡単だ」という話も聞いています。私の場合、けっこう手に汗をかきやすいので、そこらじゅうのスペアの弦を汗で錆びさせてしまう問題がありますけどね。
普通は弦の先端に結び目を作ってある弦をチェンバロ製作家から一式譲り受けたものを使うのですが、この一番切れやすい太さの弦は、私があまりに何度も何度も製作家に送ってもらうように頼んでいたら、ある時ついにリールのまま届きました。なので、この太さの弦の結び目はいつも自分で作ります。
チューニングピンに弦を巻きつけたら、金槌でカンカンと打ち込みます(2枚目の写真)。隣ではプレイエル製フォルテピアノで妻がショパンのポロネーズ3曲を練習しています。今週末のコンサートでは妻も弾くので、一人が楽器を弾いているときにはもう一人は別の作業をしているというわけです。音があまり大きくないフォルテピアノだといっても、やっぱりピアノです。金槌の音くらいでは練習の邪魔にならないみたいです。
張り替えた弦を調律し直して作業は終了。10分くらいで済んだでしょうか。新しい弦は錆びていないので、周りの他の弦に比べて音色が少し違います。よく言えば丸い、悪く言えば輝きに欠ける音です。少々の弦の錆はチェンバロの場合には音色を輝かせてくれるので悪者扱いする必要はありません。曲の中で聴く分には大して気にならないというか、気がつかない人が殆どだとは思いますが、これから少しずつ周りの弦と馴染んでいくでしょう。
追伸:
世界的名器であるこの楽器、何がどのように世界的なのか、下のボタンから詳細をご覧下さい。私の宝物です。
あなたのコメントをお待ちいたします
下のコメント欄に、ご感想、ご質問、ご意見など、何でもお寄せください。
あなたのコメントがきっかけとなって、音楽を愛する皆様の交流の場になったら素晴らしいと思うのです。
(なお、システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

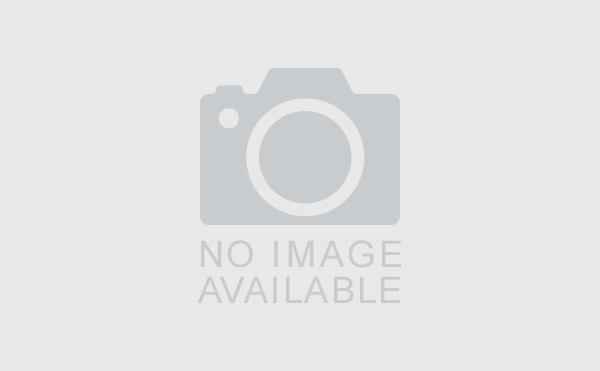
真鍮弦のリールが金色、トンカチが銀色できれいな写真ですね。
張替の作業は誰でも出来ることではないですが、先生は簡単そうにされておられます。
初めてチェンバロの生演奏を聴いた時覚えた曲がヘンデルのサラバンドでした。
今回また聴くことができるので楽しみにしています。このメロディーは私はとても覚えやすいです。
最近車の中で聴いたルイ・クープラン(1626~1661)のCDで大変似ている曲に出会いました。「組曲イ短調」の4番目Sarabanndeとありました。同じようなメロディー! 名前もサラバンド!
同じなのかなあ、違いがあるのかなあ?と思って聴いていました。
コメントありがとうございます。金色と銀色の対比はコメントを頂くまで私は気がつきませんでした。
ルイ・クープランのイ短調のサラバンドは、たしかに今回演奏予定のヘンデルのサラバンドとそっくりです。いずれもサラバンド特有のリズムの特徴をそのまま生かしています。
あっ❣今週末に演奏会があるんだ!・・・とちょっと胸が高鳴りました。
今日は月曜日だから、9月4日か5日かな?とカレンダーをみたところです。
でもちがいましたね。これは以前に書かれた記事でした。
またこのチェンバロの音色がきけるコンサートが開かれますように。
元気で運転して見附まで行くことのできるうちに。と願うばかりです。
嬉しいお言葉をありがとうございます。
コロナが収束するのをお待ち下さい。
何といってもお客様の命が最優先です。
他の方のコメントにもあるように、「週末コンサート~」を読んで、気兼ね巻くいろんなイベントに行けた頃をちょっと懐かしく思ってしまいました。
ところで、チェンバロ奏者の方がコンサート会場に持ち込むのは、楽器以外にも、今回紹介して頂いたように、不測の事態に備えて、予備の弦 (色々種類があるようですが) と、ハンマー等工具一式もでしょうか?
すみません、「気兼ね巻く」→「無く」でした。
コメントありがとうございます。
チェンバロを運ぶ時は、そもそも脚を分解したり組み立てたりするのに工具が必要ですし、当然調律道具も必要です。そのほかにも、環境が変わるといろいろな不具合が起こりますから、必要な道具一式を工具箱に入れていつでも楽器と一緒に持ち歩いています。
こんにちは♪弦を巻き付けてピンを打ち込みますがピンホールが大きくなってルーズピンになったリハするのでしょうか?
コメントありがとうございます。
おっしゃるように、同じ弦を何度も張り替えていると、ピンホールが大きくなってピンが止まらなくなります。そういうときはカンナくずをピンと一緒に打ち込みます。