私はこの曲のせいで脱サラしました
チェンバロ演奏家になる前、私はある機械メーカーで設計の仕事をしていました。
子供のころから工作は好きだったし、理屈っぽい性格でもあったので、大学は工学部で機械工学を学びました。(両親から「音楽家などを目指して人生を棒に振るものではない」と言い聞かせられていたこともあります。)大学院まで進んで機械工学を勉強した後は、エンジニアになるのはごく自然な成り行きでした。
始めのうちこそ希望に燃えて設計の仕事を頑張っていた私ですが、少しずつ音楽への情熱が高まっていきました。会社の独身寮に持ち込んだ小さな練習用のチェンバロを休日に弾くくらいでは、私の気持ちは収まりません。
入社して6年目の秋ごろになると、会社で仕事をしていても頭の中はバッハの音楽でいっぱいでした。
ある日のことです。CADの前に座って図面を描きはじめるとすぐに、頭の中にバッハのオルガン曲が流れ始めました。有名な「パッサカリア ハ短調」です。通して演奏すると12分かかる大曲です。
この曲は子供のころから好きで、私はもう隅々まで暗譜していました。だから、頭の中にこの曲が鳴り始めると、最後の音まで頭の中できっちり再現されてしまうのです。その12分間はCADを操作する手は完全に止まっています。そして、とめどもなく涙が流れるのです。
機械の図面を描きながら泣いているわけにいかないので、「ちょっと現場に行ってきます」とか言ってヘルメットをかぶり、現場に行くふりをして手洗い場で涙にぬれた顔を洗いました。そして気を落ち着けて部屋に戻り、CADの前に座ると、またバッハのパッサカリアの冒頭が頭の中に鳴り始めるのです。そしてまた12分間、手は止まり、涙がとめどもなく流れます。
「こんなことを定年まであと30年間続けることはできない」と観念して、私は会社を辞めました。「この先どうなるんだろう?」などと考えても仕方がありません。とにかくその時の私は、頭の中にバッハの音楽が鳴り始めると何も手に付かなくなって涙があふれてくるのですから。
今にして思えば、「音楽家として人生を再出発するなら、手遅れにならないうちに始めなさい」とバッハが導いてくれたのかもしれません。
では、そのパッサカリアの演奏をお聴きください。
あなたのコメントをお待ちいたします
下のほうのコメント欄で、あなたのお考えをお聞かせくださると嬉しいです。
(システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

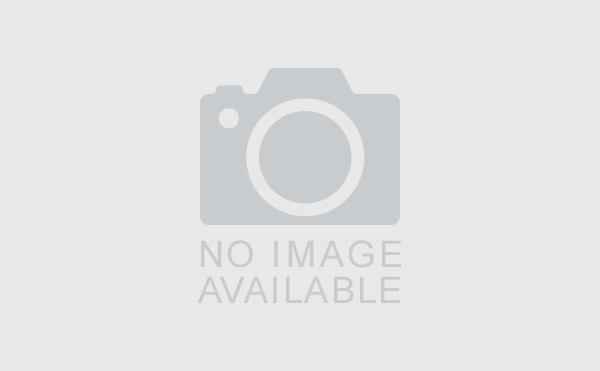
心に「バッハ」の曲が溢れてくる、というのは先生がバッハに関して天才の資質を
お持ちだという証拠だと思います。今のお仕事に結びついて将来大きな花を咲かせると拝察しま
す。私は大学卒業後、東京バッハ合唱団に入り、指揮の小林道夫氏(チェンバリスト)からバスのソリストとしての才能があるので声楽家の道を行ったらと勧められましたが、就職したばかりで日立製作所の新入社員として歩み始た「システムアナリスト」の道をまっしぐらで一生を進みました。妙高高原に転居し「新潟バッハ合唱団・管弦楽団」で先生にお教えいただき、その後退団してからも新潟バッハ合唱団・管弦楽団の演奏会のプログラム解説を書かせて頂いています。
ありがとうございます。
そのような経歴をお持ちとは存じ上げませんでした。バッハへの強い情熱をお持ちなわけですね。
導かれるように音楽の道に戻ってこられたのですね、、貴重なお話ありがとうございました。パッサカリア、きいたことはありましたが通して初めて聴きました。心に深く入ってくる演奏ですね。子どもの時に好きだったものは生涯変わらないですよね。
コメントありがとうございます。私はこの先も生涯ずっとバッハに狂ったチェンバロ弾きなのだと思います。
こんにちは。メルマガで「なぜ音楽が冷たい?」を拝読しました。
以下は、チェンバロではなく、ピアノのお話です。
私は昨年秋から自分でピアノを調律しています。
調律だけでなく、ハンマーやアクションや鍵盤などのメンテナンスもしています。
うちにあるのは、2014年に新品で購入したヤマハC3Xです。
2000年ころを境にヤマハの品質はガタっと落ちたようで、白鍵剥がれをはじめとする(白鍵剥がれに限らない)トラブルが多く発生しています。そのような粗雑さをつゆ知らず買ってしまい、特に白鍵剥がれでは我が家では発生から解決まで2年もかかり、大変な思いをしました。
残念ながら、有鬚な調律師にも出会えませんでした。独立系、大手楽器店系とも。つまり、調律しても音がガタガタ。また、調律師にタッチ感や音量コントロールやペダリング調整のできなさを伝えても、調律師の聴力的に聞こえていないし満足な演奏能力もないので問題が問題と認識できず、直せなかったのです。
購入から10年たった昨年、とても使える代物ではなくなってきたため、やむなく高級電子ピアノに買い替えを検討しはじめました。
同時に、最後に自己責任のダメもとでDIYを試しました。これが上手くいきました。そのため、今でもC3Xを使い続けています。
昨年秋以降、調律に限ると、鍵盤全体は月2回程度。時々個別に音程を整えています。
先生のように、毎日、録画中にも、という訳にはいかないのですが・・・。
タッチ感も劇的に改善。
一日数時間弾いても手首や腕が痛まなくなりました。
ピアノの調律その他のメンテナンスは、根気と時間さえあれば、作業自体は単純です。
適切な調律アプリ(piano meterなど)をダウンロードし、専門の道具を専門店で(アマゾンではない)購入し、Howard Music Industriesなどの動画が、助けになります。
調律をレトロな音叉で使って行うことにこだわる日本人調律師が多いのは、謎です。2000年ころのドイツの調律師の間では、すでにその方法では不正確なので、廃れていました。私もアプリを使っています。
調律師の試験で±5セントで測るのも、問題です。音は落ちるので、-を合格の範囲に入れる必要はないからです。
DIY調律の良いところは、自分自身で屋内外が静かな時間帯を選べることです。
風雨や車などの騒音の中で、決まった時間内に調律するなど、今となっては信じられません。
今、ローランドのLX6など高品質な電子ピアノ(サンプリングではなく周波数をモデリングしている、音の反響やタッチ感も変えられる)や、スマホの音楽アプリに、人気が移っています。
その方が音楽を楽しめるのであれば、それでよいと思います。
ただ、DIYという解決方法もあることは、世に広まってほしいと思います。
長文失礼いたしました。先生のますますのご活躍をお祈りいたします。
ご丁寧なコメントをどうもありがとうございます。
私はずっと「チェンバロと違ってピアノの調律は素人には無理」と聞かされていましたから、コメントを読んで認識を新たにしました。