ピアノが大事?バッハが大事?
八百板さんがビデオで説明している弾き方はチェンバロを前提としていると思いますが、ピアノでもそう弾くべきなのでしょうか?
私のビデオをご覧になったお客様から、時々いただく質問です。
どうですか? あなたはどうお考えですか?
じつはこれ、とても根が深い問題なのです。チェンバロが復興した20世紀後半からずっと議論されているホットな話題で、ピアノを弾く人の中でも賛否が分かれます。
あるピアニストはこう考えます。「私がバッハを弾くのは、私のピアノを美しく響かせるため。」
別のピアニストはこう考えます。「私がピアノを弾くのは、バッハの頭の中に鳴っていたであろう姿に迫るため。」
20世紀の半ばまでは、ある意味で状況は単純でした。世の中にはチェンバロが無かったと言ってもいいほど少なかったし、バッハの時代にはどう演奏されていたかも知られていませんでした。ですから、ちょっと乱暴な言い方をすれば、ピアノで弾いて美しく響く弾き方をしてさえいれば良かったのです。
その路線で、今は亡き偉大なピアニストたちによるバッハのレコードの名盤がたくさん生まれました。過去の偉大なピアニストたちが弾くバッハは、ピアノ音楽としてとても高い境地に達していると私も思います。
やがて、20世紀の後半にチェンバロが復興しました。そして、こちらの方がより重要なのですが、バッハの時代にはどう演奏されていたかという「演奏習慣」についての研究がとても進んだのです。バッハ自身は鍵盤音楽の楽譜にほとんどスタッカートやスラーなどを書かない人でしたが、「バッハの時代の人々は、このように楽譜が書いてあったら、このように切ったりつなげたり、テンポを揺らしたり、装飾音を即興で加えたりしていたらしい」ということがかなり詳しく分かるようになったのです。
チェンバロ奏者たちはもちろんその「演奏習慣」の研究を自分たちの演奏に大いに役立てました。バッハの時代の楽器を、バッハの時代の人々の弾き方で演奏することで、バッハの頭の中に鳴っていたであろう姿に少しでも近付くヒントにしようと努めたのです。
結果として、チェンバロ奏者たちが弾くバッハは、それまでのピアノで演奏されていたバッハとは、まるで別の曲かと思うほどに違う姿となりました。
チェンバロが復興した当初は、音楽界から「しょせんは博物館から引っ張り出した懐古趣味だ」と言われて相手にされませんでした。それが、少しずつ少しずつ聴衆の支持を得ていったのです。そして20世紀の終わりごろには、「バッハ」といえば「ああ、本来はピアノではなくてチェンバロのために作られたんでしょ?」と当たり前のように知られるほどになりました。
そうなると、ピアノを弾く人たちの間でも、チェンバロを無視する事ができなくなってきました。今では、チェンバロ奏者のように「私が弾くのはピアノだけど、バッハの頭の中に鳴っていたであろう姿に迫りたい。」という人も増えつつあります。
まとめましょう。「ピアノでバッハを弾く時にチェンバロ奏者のように弾くべきか?」と問われたら、私は「立場によって、どちらもあり得る」と答えます。現代のピアノという楽器の響きを優先するのか、それともバッハの頭の中に鳴っていたであろう姿を優先するのか。
今、時代の流れは確実に後者に向かっています。山形交響楽団がシューマンの交響曲でピストンやバルブの無い19世紀の金管楽器を導入したり、東京交響楽団がブラームスの交響曲でブラームスの時代のオーケストラの配置を採用したり、あのショパンコンクールにもショパンの時代のピアノを使った部門ができたり。
ピアノでチェンバロという「楽器の真似」をする必要はありません。バッハ自身がどんな演奏を望んでいたのかを学んで、あなたのピアノ演奏に活かしてください。
追伸:
バッハの時代に、あの何も指示が書いてない楽譜から具体的にどんな演奏がされていたのでしょうか?「当時の演奏習慣」について本気で学びたい人は以下のページもチェックしてみてください。
あなたのコメントをお待ちいたします
下のほうのコメント欄で、あなたのお考えをお聞かせくださると嬉しいです。
(システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

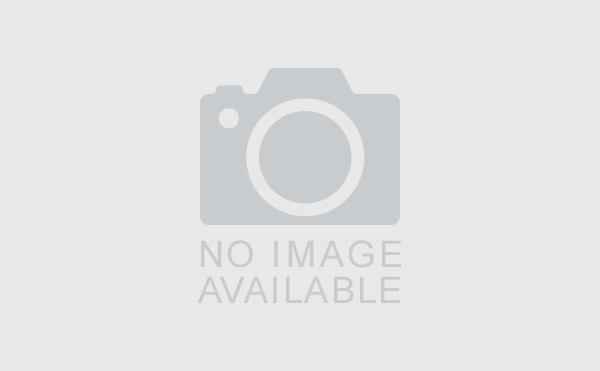
ありがとうございました。
私が師事している方は「どんな風に弾いても良いけど、バッハが現代のピアノを弾いたらこう弾くかな?と考えて私は弾きます」と話されていました。
バッハなら、ピアノという特性に合わせた音楽を頭の中で鳴らすのでは?と思うので、自分が好きと感じる弾き方で弾こうと思います!
最終的には自分の耳を頼りに楽器と対話しながら表現を練り上げていくことになりますね。
その時の基準のひとつとして「当時はこういう楽器でこう弾いていた」ということを知っていただくために、私の演奏と解説を利用してくだされば嬉しいです。
楽器の進化はチェンバロやピアノのような鍵盤楽器だけではなく、全てに言えますよね。
ベートーベンの時代のホルンは、演奏の途中で管を交換しなければならなかった。
作曲家は当然、交換作業が可能な時間を計算して作曲しているわけで、奏者も間に合うよう準備しなければならない。
仮に十分なユトリある構成だとしても、「あそこで取り替えなきゃ」という緊張感は、相当に大きなプレッシャーになったはずです。
その必要が無い現代の楽器とでは、ステージ上のマインドを当時と同じには出来ません。
世に電気ピアノが出現した時、音域はF2~f3の61鍵で、これはモーツァルトとベートーベンの初期と全く同じでした。
が、音大ピアノ科の学生たちは、「こんなに鍵盤数が少なかったら、何も弾けやしない」と、
見向きもしなかった。かくいう自分が左様でした。本当は十分、バッハが弾けたのにね。
電気処理上、ピアノよりもチェンバロの方が音を似せやすかったので。現場ではリズムギターの代用に使われました。スティービー・ワンダーが一躍スーパースターになったのは、その可能性を誰よりも巧みに演奏したから。彼がリュートとチェンバロの互換性を知っていたか否かは勿論分からないですが、それの現代的な奏法を試みる辺り、やはり凄い天才だと思います。
コメントありがとうございます。
ホルンの替え管の話は私も知っています。
ピアノの音域の話ですが、バッハが4オクターブでほとんど弾けるとか、モーツァルトが5オクターブで弾けるということを意識していない人は多いですよね。作曲家にとっては「最高音」「最低音」はすごく大切なことなのに。
これからもたくさんコメントして、いろいろ教えて下さいね。
今のホルンはヴァルヴがあるので替え管の必要はなくなっていると思いますが
ティンパニは楽章ごとに、中には楽章の途中で音律を変える必要のある曲がありますね。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番と第2番(ピアノの高音域がf3までだった時代の作品)に
後からベートーヴェン自身が書いたカデンツァは、高音域が広すぎて
初演当時のフォルテピアノでは演奏できないので演奏者が自作した、と
手許のCDの解説に書いてあります。
ティンパニは、今では4つくらい並べておいて、できるだけ曲の途中で音の高さを変えないで済むようにしていますね。
ベートーヴェンの時代は、交響曲は楽章ごとに拍手を受けて演奏が中断していましたが、今はそういうこともなく楽章間に時間の余裕がありませんから。
興味深くかつ本質的な問題提起をありがとうございました。チェンバロの復興史については詳しく知らず、勉強になりました。
個人的には「バッハが表現したかった(頭の中の)音」が先にあり、それを表現する手段としてモダンピアノなどの楽器がある、と考えています。私は楽器店での試奏ぐらいしかありませんが、例えば別記事で触れておられるような弦楽器の経験は大きいと思います。
もちろん、一口にモダンピアノと言っても、フレームのつなぎ方、弦のピンどめの仕方など、構造によって受け継いでいるルーツは異なるでしょう。どのメーカーを嗜好するかで立場の違いが現れるかもしれません。
コメントありがとうございます。
同じモダンピアノと言っても、ベヒシュタインやベーゼンドルファーといったヨーロッパのメーカーの楽器は、昔のフォルテピアノ(もっと遡ればクラヴィコード)と共通するものを感じる、という話も聞いています。
はじめてコメントします。
私自身は鍵盤楽器は全く弾けない(バイオリンは少々)のですが息子がピアノを習っていてバッハで苦労しているのを見ていてこちらにたどり着きました。
「バッハの時代の演奏習慣」というのはどうやって研究されるのでしょうか。
演奏の音そのものが残っているわけではないと思うのです。
バイオリンでも同じように「当時はこうやって弾いていたはずだ」という議論をよく目にするのですが、同じ疑問をいつも抱いています。
コメントありがとうございます。
昔の演奏習慣についての一番の情報源は、当時の文献です。
出版された音楽理論書にはかなりの情報が詰まっています。
また、音楽家どうしがやりとりした手紙なども重要です。
演奏家はそういったものを直接古文書館で発掘して読み解く時間の余裕がありませんが、代わりに音楽学者たちが気の遠くなるような文献調査をしてくれています。
原典版として現代に出版される楽譜の解説などにも、そうした研究の成果が載ることもあります。
ただ、研究者は演奏家ではないので、議論のための議論ばかりが独り歩きすることもあって、彼らの言うことを鵜吞みにすることはできません。
最終的には、演奏家個人が自分の責任において判断することになります。
文献や手紙のやり取りなんですね。
「音が残っていないと分からないのでは」と思うのは、素人考えでした。
一度失われた楽器で、一度忘れ去られた曲を弾こうというのですから、まるで考古学のような研究が地味に続けられています。
バッハの平均律クラヴィーア曲集は、ベートーヴェンも、充分研究して、後期のピアノソナタに活かしているし、ショパンも前奏曲集作品28に於いてバッハの平均律クラヴィーア曲集を意識していた。ドビュッシーも前奏曲集一巻とニ巻をやはり、意識にあったと思う。ラフマニノフやスクリャービンも前奏曲があるが、ピアノ練習曲も兼ねてショパンの前奏曲がおそらく意識していたと思う。ピアニズムが発達した時代だったのだろう。バッハの平均律クラヴィーア曲集は、最初の方は、ハ長調から同主短調のハ短調と言う規則性があるが、一つの楽曲の中に部分的に転調もあり得るので調律によって弾けないと困るから今現代よりも調律は大事であったと思う。ショパンは、練習曲こそ調性は、完全に規則性はないが、前奏曲は、5度圏を上げている。バッハの時代の鍵盤楽器の調律は、異名同音の調は厳密に言うと異なった調であり、例えば、平均率の調律では、フラット系の調FesDur
は存在しないで、シャープ系の調EDurと言う事になる。
同様にフラット系の調CesDurは、シャープ系の調H
Dur と言う事になる。おそらくバッハの平均律クラヴィーア曲集とは、良く調律されたと言う意味があるのだと思う。すると、現代の平均率に調律されたピアノでは正確な表現が出来ないのかも知れないが、
バッハの時代の調律に合わせたピアノまたは、鍵盤楽器なら上手く弾けるはずだけど、標準が、平均率であるから、できる限り、バッハの弾き方を真似たり、響きをピアノ奏者がテクニックでカバーして演奏するしかない。
ご丁寧なコメントをありがとうございます。
調律法について、私は以下のように考えています。
バッハの時代の各種の古典調律では、ヘ長調は牧歌的な響き(3度の唸りが少ない)、ホ長調はギラギラと浮足立ったような響き(3度の唸りが我慢できる限界まで多い)などという違いが生じます。
でも平均律では、ヘ長調もホ長調も同じように弾けば同じような響きになります。
ポイントは「同じように弾けば」です。
物理的な3度の唸りの周波数では同じでも、「当時の調律法では牧歌的な響きがしたのだから、牧歌的に弾こう」と演奏に反映させるなら、違う音楽になるのです。
普通の聴衆は3度の唸りの大小に注意を向けたりしません。
けれども演奏者が込める「牧歌的」「浮足立った」という表現にはきっと気が付くはずです。
だから、平均律の楽器を弾くにしても、バッハの時代の調律法の知識は大きな武器になると思うのです。
いろいろな考えがありますね
ピアニストさんによってはバッハの時代にピアノがあればバッハは絶対ピアノを弾いた!ということでその方はあえてピアノだそうです
私はどちらも素敵💖選べない〜派です
その時代に生きた作曲家がどのように演奏したか!というテーマは永遠で素晴らしいことと思います
ド素人の私でも浪漫を感じるテーマです
ありがとうございます。
浪漫!
そうですね。私にとってバッハの復元は考古学のようなロマンを感じます。